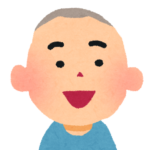
外部進学時の院試対策はどうやってしたの?



いつから対策をはじめたの?
こういった疑問に関して少しでも参考になるように私の実体験を書きました。
大学院進学では、同じ大学からそのまま進学(内部進学)する人がほとんどです。
違う(外部の)大学院に進学する人はほとんどいないため、外部進学の情報が少ないと思います。
外部進学を目指している方に向けて、大学院入試(院試)関係で私が行ったことをまとめました。
院試も、筆記重視や面接重視など進学先によって大きく異なると思いますので、一つの体験談として、参考に見ていただければと思います。
大学院を変更した理由、メリット・デメリットなどはこちらにまとめています。


今回は大学院入試(院試)に特化した内容を書いていきます。
私の外部進学先について
(大学)某地方旧帝大工学部土木系の学科
↓
(大学院)関西の某旧帝大学院の工学部土木系の学科
同じ工学系の学科で大学院を変更しました。大学と外部進学した大学院ともに同じような研究テーマでした。ちなみに、修士課程を修了して就職し、博士課程には進学していません。
大学院入試までの流れ
8月~9月あたりに入試試験があるのが一般的だと思います。
私の場合は、内部進学先と外部進学先をそれぞれ1校ずつ、合計2つ受験申請しました。外部進学先の方が先に合格の結果が出たため、内部進学先の院試は結局受けずに終わりました。
院試の受験日から逆算して計画を立てていくことが基本となります。
私の場合は、下記のスケジュールで動きました。
| 大学3年 1~3月 | ・TOEIC対策を完了 ・外部進学先の研究室について調べ始める(主にHP) |
| 大学4年 4月~ | ・院試科目の勉強スタート |
| 5月~ | ・外部進学先の研究室訪問 ・志望理由書などを記入 |
| 6月~ | ・願書関係の書類作成、提出 |
| 7月~ | 【面接対策の対策を始める】 ・外部進学先の研究テーマ調べる ・研究先のテーマで気になった論文を数本読む |
| 8月~9月 | ・大学院入試 |
院試対策について
外部進学の院試対策について、以下の3点にわけてそれぞれみていきます。
- 研究室訪問
- 筆記試験(TOEIC対策)
- 提出書類(志望理由書など)
- 面接対策
研究室訪問【外部進学の院試で一番大切】
外部進学の際に一番大切なことは、研究室訪問だと思います。
研究室訪問・担当教員に挨拶に行くことによって、志望する研究室の雰囲気や大学院での生活スタイルが、ある程度わかります。
また、その大学独自の院試対策なども教えてもらえる可能性があります。(後でもう少し詳しく書きます)
大学院生活では研究室での生活がメインになるので、研究室の環境や指導教員の雰囲気などを見るためにも、絶対に一度は訪れておいたほうがいいと思います。
私の場合は、5月のGW明けに希望する研究室の教授に研究室訪問のアポをとる依頼メールをしています。
過去のメールがありましたので、そのまま貼ります。コピーしてお使いください。
今思うと内容があっさりしていると思いますが、失礼なく訪問日程のアポ取りができればいいと思います。
○○先生
はじめまして
○○大学△△学部~~学科4年生の○○○と申します.
突然,ご連絡させて頂いて申し訳ありません.
私は現在,所属している~~研究室において,~~,及び,~~~~に関する研究をしております.
そのため,~~の研究に非常に興味があります.
貴大学のホームページを拝見いたしまして,研究内容や大学院進学等についてお話を伺いたいと思い,ご連絡を差し上げた次第です.
ご多忙中,恐縮ですが,先生のご都合の良い時に見学のお時間をいただけませんでしょうか.
どうぞよろしくお願い致します.
このようなメールを送りました。その後、メールのやりとりをざっくり表すと
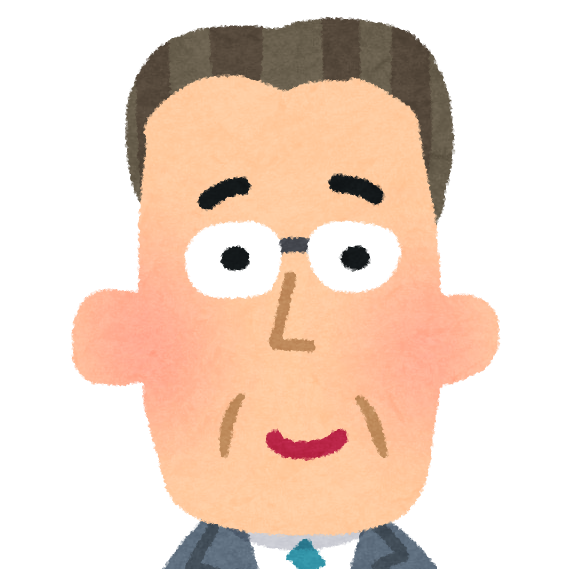
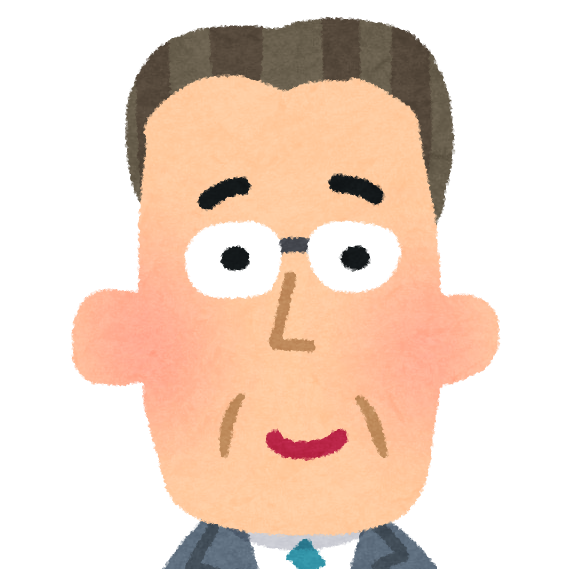
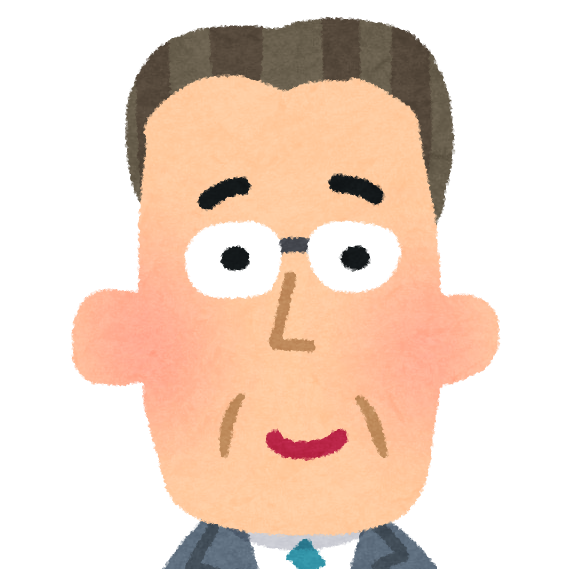
OK。○日と△日と□日はどう?



○日に行きます
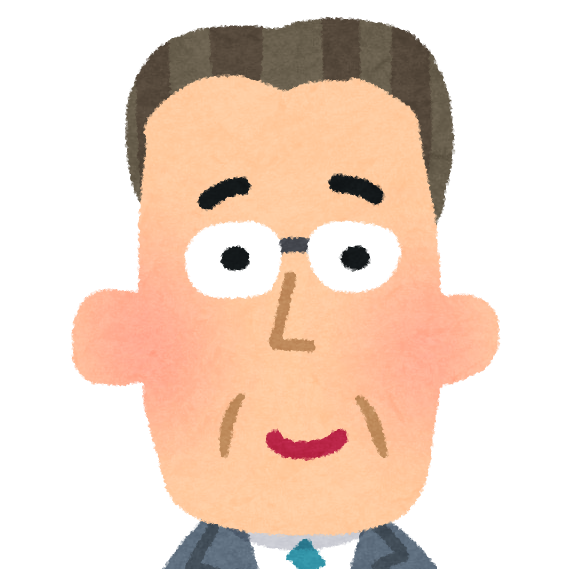
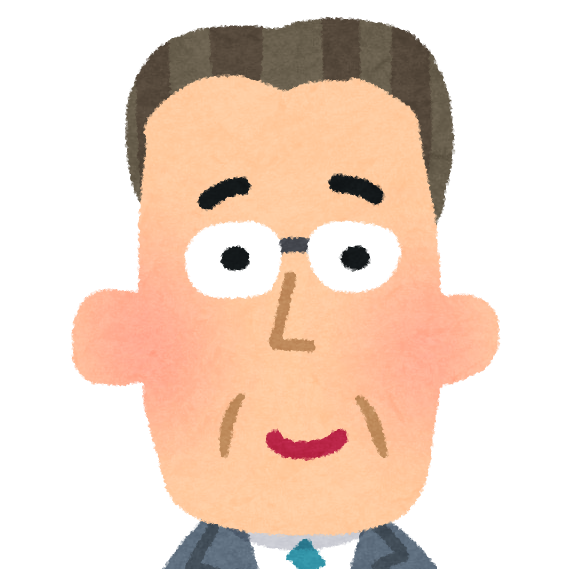
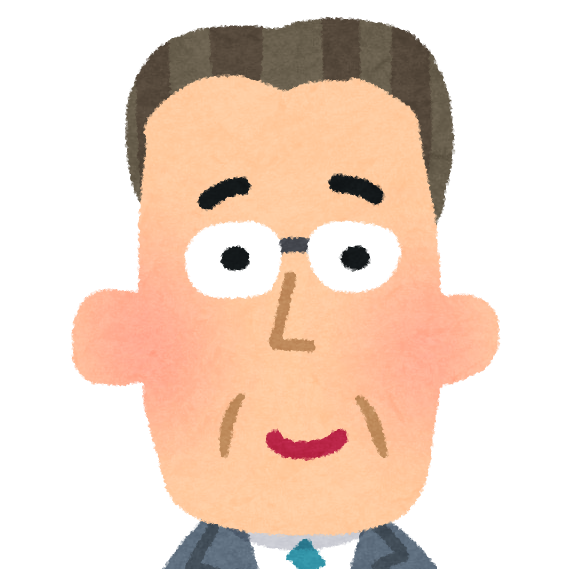
OK。それまでに余裕があれば入試要項みといてね。



わかりました
その後、指定の日時に研究室に行きました。一応、地元の手土産も持っていきました。
先生から研究室の概要・各研究テーマ・研究室のメンバー紹介をしてもらいました。
説明の後、どんな研究をしたいか、就職はどう考えているのかなどを聞かれました。
研究については、聞かれると思い準備していたので、準備内容をそのまま答えました。
将来は「今の時点で決めていない」と答えました。外部からくるので、「博士課程まで進んで研究者になりたい」という答えを先生は望んでいたのかもしれませんが・・・笑
その後、学生さんのいる部屋に連れて行ってもらい、プチ交流会をして解散となりました。
帰り際に先生からは研究プロジェクトのパンフレットと、学生さんから過去問をもらいました。過去問は、数年分の過去問と解答がセットになった一式データをUSBに移してもらいました。
過去問を(できれば解答も)もらえるかどうかというのが、院試攻略に向けて一つの「カギ」になると思います。
今回は聞かなくてももらえましたが、訪問の際に過去問があるのか聞くともらえたりして、対策がしやすくなると思います。
- 研究室の訪問の際には、希望する研究室の研究分野・テーマなどを最低限予習してからいくと好印象です。
- 訪問時に聞きたいことはメモにして持っていきましょう。
- 受験前と受験後も、担当の先生と何回かメールでやりとりが必要な場面がでてきます。
- 訪問時の1回きりで終わらないこともあるので、メールのやりとりで齟齬が発生しないように気を付けましょう
研究室訪問によって、研究室・先生の雰囲気も良かったので受験しようと決意し、次の日にお礼と受験しようと思う旨のメールをしました。
そこから、1~2か月経過した際に、担当の先生から提出する志望理由書などをチェックしようかとメールで連絡がありました。
既に提出していたのでその旨を伝え、チェックしてもらえなかったのですが、志望理由書や研究経緯などの書類についても、事前に担当の先生に連絡を取ってみてもらうのも良いかもしれません。
筆記試験対策(内部進学の院試対策がメイン)
筆記試験についてどのように対策を行ったのか書いていきます。
基本的な筆記試験は、内部の進学先の院試対策をメインにして勉強しました。
国家総合職(技術系)も同時に受けていたので、国家試験対策と院試対策とあわせて勉強していました。
内部進学用に試験対策した理由としては、外部進学先からもらった過去問を見ても、出題範囲・レベルなどに大きな違いがなかったからです。(内部・外部進学先において学科・コースが同じだったことが大きいです)
内部進学を100%受かる状態になれば、外部進学の院試もある程度勝負できると思っていました。そのため、外部進学に向けて特別な試験勉強は行わず、内部進学用の試験対策を繰り返し行いました。
外部進学先の勉強としては、2週間ほど前になってから過去問を2~3年分解いただけでした。
外部先の過去問を入手できれば、対策はかなりたてやすくなるとおもいます。
TOEIC(英語)対策について
TOEICは、院試に必要な大学院が多いと思います。私の場合は内部・外部進学先のどちらも必要でした。
就活でも必要ですし、TOEIC対策を後回しにするとバタバタするので、なるべく早い段階で(3年生の終わりには)自信のあるスコアまで持っていきたいですね。
私は大学3年冬に受けた780点くらいのスコアを院試に提出しました。
私が行った対策といえば、公式問題集を数冊買って、それぞれ何周もするだけです。
一般のTOEIC参考書より、公式問題集の方が問題の質も含めて良いと思います。
駿台の浪人時に参考書を何冊も出している某有名講師が、「センター試験(共通テスト)過去問とセンター試験(共通テスト)模試問題集では問題の質が全く違う。見た目は同じでもカレー味のカレーか、う○こ味のカレーくらいに違う」と言っていました。
実際に、同じように見えても問題構成がこう違う(過去問の方が予想問題より質が良い)といったプロの予備校講師ならではの解説をしてもらいました。
同じようにTOEICも公式問題集の方が、市販の参考書より、洗練されている良質な問題が多いと思います(プロじゃないので違いがそこまでよくわかりませんが・・・)。
公式問題集を完璧に解けるまで何回も繰り返すだけで、800くらいまでは狙えると思います。
公式問題集シリーズがおすすめです。
提出書類(志望理由書・研究計画書など)
志望理由書は、関連書籍を参考に、数日に分けて少しずつ書き足していきました。
自分で納得のいくものに完成させて、最後に誤字脱字をチェックし、そのまま提出しました。今思うと、自分以外の人に見て、意見をもらうとよりクオリティが上がりよかったと思います。
面接対策
面接は対策用に、本を一冊買って読みました。
数日前から対策を開始し、志望理由・研究計画書などの提出した資料や志望する研究テーマについての想定質問を何問か作成し、スラスラ言える状態にしました。
面接時の格好は黒のスーツで行きました。他の人もスーツでした。(当たり前ですが・・・)
実際の面接時には、以下の点を聞かれました。(覚えている範囲です)
・筆記試験はどうだったか、感想は?
・修士課程でしたい研究
・志望理由書の深堀り
・将来博士課程の進学は考えているのか、就職したい場合は、どういった分野を目指しているのか
それなりに答えて面接は終了しました。
合格後は・・
合格を確認した後、すぐに担当の先生にメールを入れ、アポを取って研究室に挨拶に行きました。
私と同じ進学する同期はそのまま連絡をほったらかしにして、怒られていたみたいです笑。2年間お世話になるので、連絡はこまめにしておきましょう。
引越し先の物件などは年明けくらいから探し始めました。
感想~効率的に院試対策をするには~
院試を通じて、研究室訪問が一番大切だと思います。ネットに載っていないリアルな情報を教えてもらえたりします。
外部進学にあたって、院試の試験自体はそこまで難しいとは感じませんでした。ただ、研究室を訪問したりするので、遠方だとそれなりに労力はかかります。
院試の筆記対策より、どちらかというと、研究室の研究内容を調べたりする準備にある程度時間をかけましょう。
大学院や専攻によって状況が違うかもしれませんが、私が受けたところは外部進学者が不利という感じではなかったです。たぶん内部・外部進学どちらも合格しやすいコースでした。
外部進学が不利だというネット情報も多いですが、私の受験先は外部進学生ウェルカムな感じでした。
受験先によって違うと思うので迷って外部受験をやめるぐらいなら、とりあえず受ける準備をしてみるのも、”あり”なのではないでしょうか。
私が外部進学した大学院のコースは、就職する4年生の補充も兼ねて外部から入学させているようです。
なので、外部から積極的に補充したいため、そこまで倍率は高くないようです。
※外部進学先によって状況は異なるので、あくまで私の外部進学先の話です。
筆記試験対策としては、過去問の入手が重要です。過去問は、部外にはあまり出回らないからです。過去問の解答はもっと出回っていないので、手に入れることができれば、徹底して対策することで合格に近づくと思います。
私のように同じ学科・コースの外部進学だと、内部進学用の院試対策を行うだけでもある程度通用すると思います。
面接は、面接の際に聞かれる提出書類(志望理由書、研究計画書など)を自分が納得できるレベルまで作り込むことが大切です。
まとめ
私が外部の大学院入試を受けた際の経験をまとめました。
内部進学と比べて労力もいるため、外部に進学する人は少ないですが、勇気を出して外部に進学するのも選択肢の一つだと思います。
早め早めに1つずつ院試に向けた行動をとることが大切です。
迷っている方にとって、1つの参考になれば幸いです。
忙しい日々のマネジメントに関しては、以下の手帳がおすすめです。私も愛用しています。
健康が第一だと思います。健康関連でオススメの本です。健康に留意して院試対策を乗り切ってください。
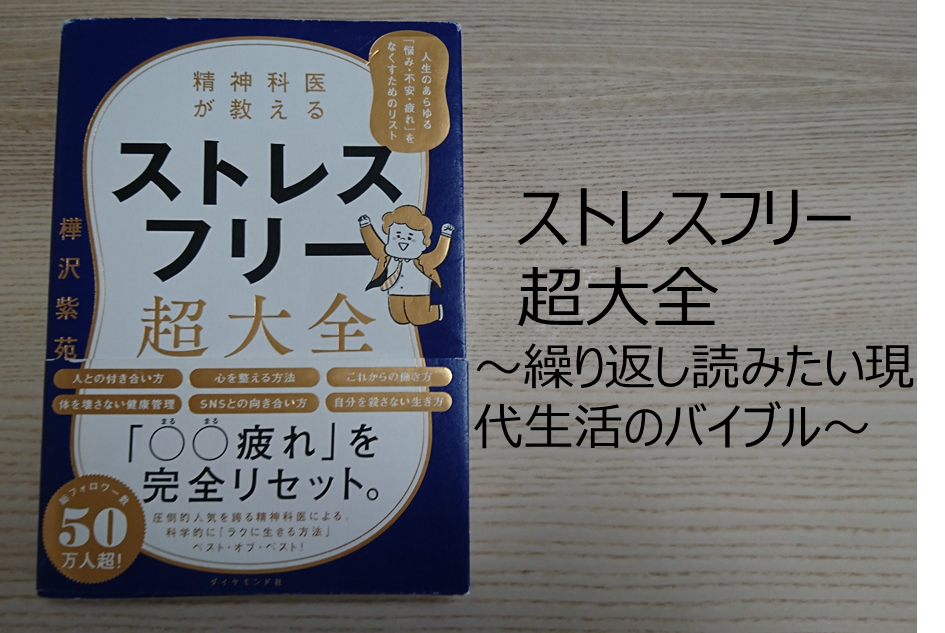
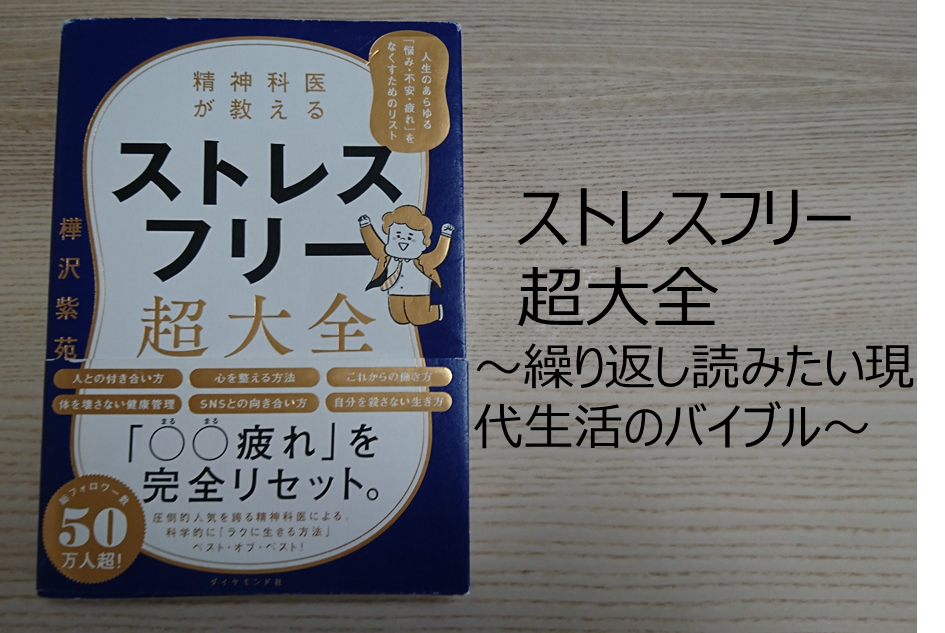

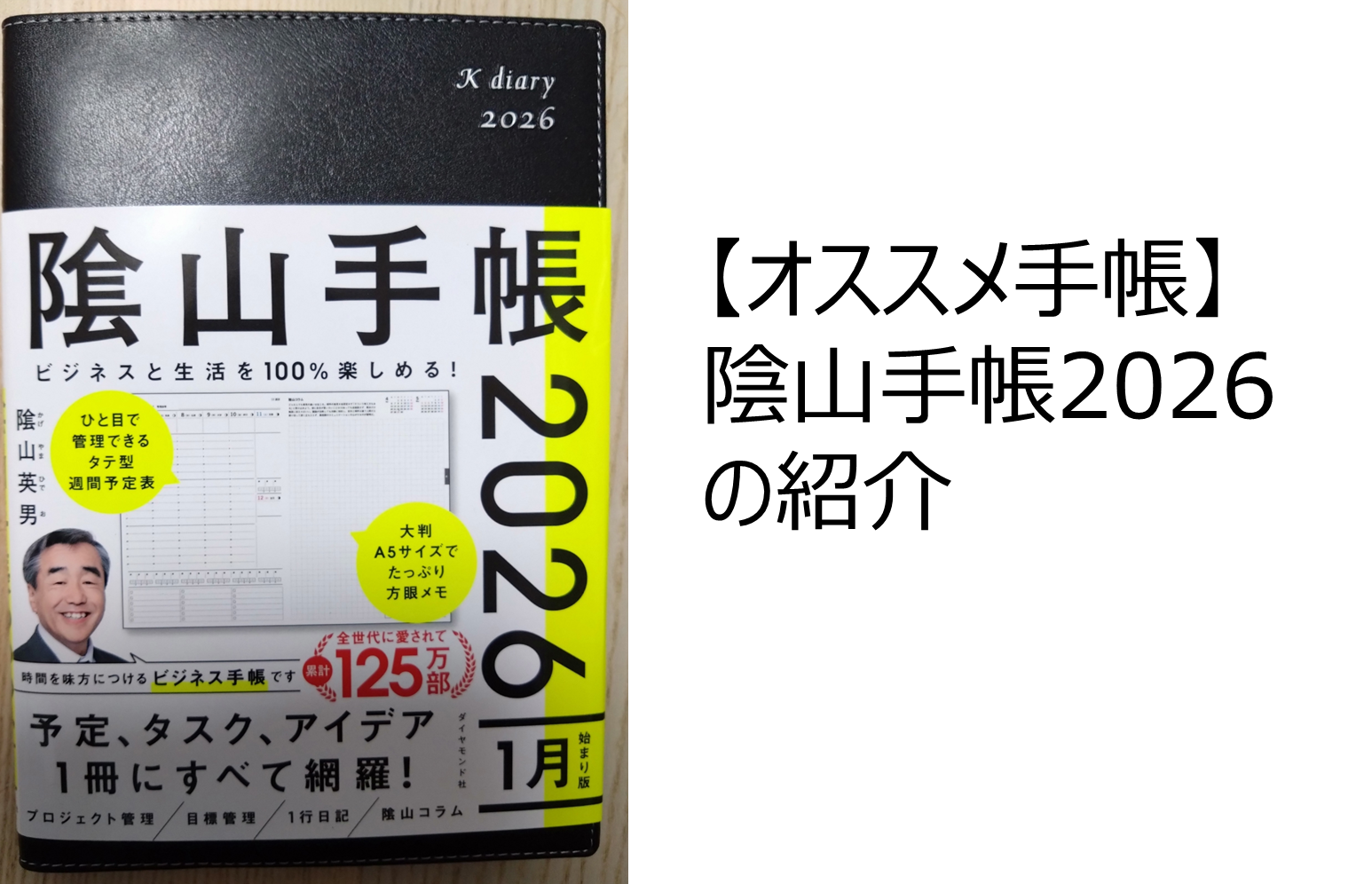
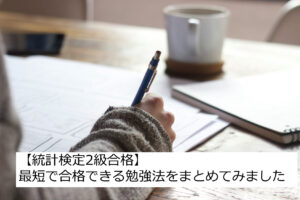
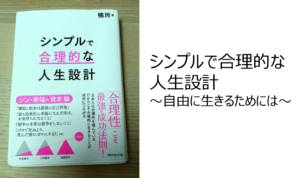
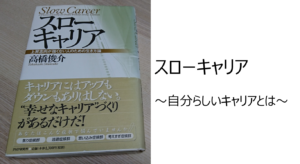
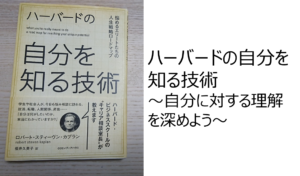


コメント